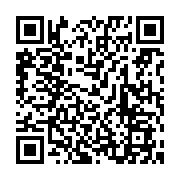【個人事業主を目指す方は必見】開業したら役所と税務署へ!開業届の書き方と5つの手続き手順について
公開日:2018.10.9 | 最終更新日:2025.6.3
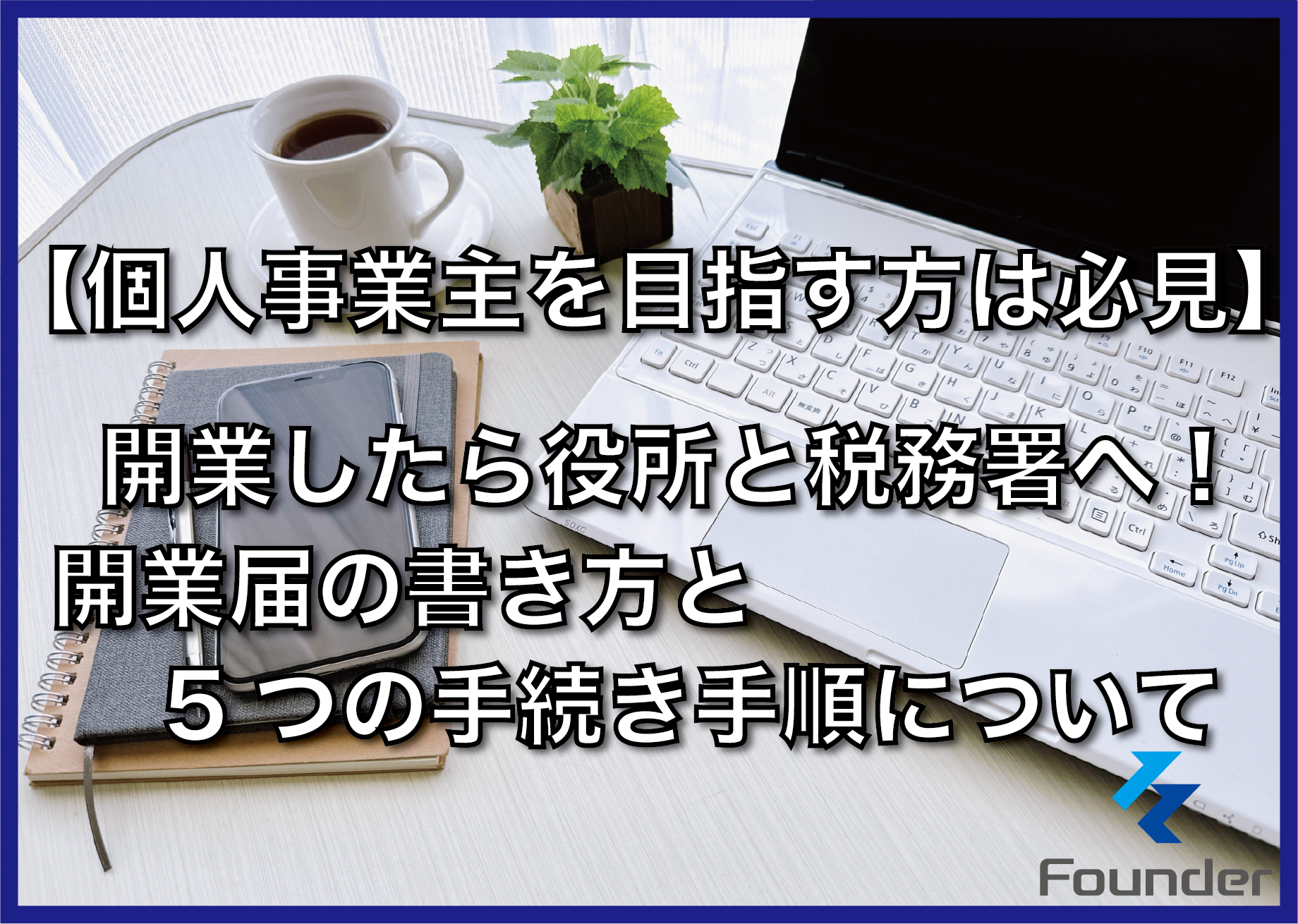
「個人事業主として晴れて開業!」と喜んでいる方もおられるかもしれませんが、第三者に開業を証明するためには「開業届」の提出が必要です。
また、最近では副業を始める人が多いですが、あなたが会社員であっても、副業を始める場合は個人事業主になるための開業届けを提出する必要があります。
副業でも開業届を出すことが義務であることはあまり知られていません。
開業届と聞くと難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえておけば誰でも簡単に作成できます。税制面でのメリットもあるため、個人事業主の方は1つずつ準備を進めていきましょう。
今回は、個人事業主の開業届の書き方や手続き手順を徹底的にご紹介します。初心者向けに解説しているので、初めての起業でも100%内容を理解できます。
※ なお、独立開業をする為の資金が必要なら、SMBCモビットなどのカードローンへの申し込みがオススメです。
スマホやパソコンからネットだけで5分でカンタンに申し込みが完了します。あなたも100万円のお金を手に入れることができるので、今すぐ以下のリンクをクリックして申し込んでください。
【1番人気】SMBCモビットは来店不要で審査が完了。スマホアプリでカンタンに出金が可能です。
※アクセス数などを参考に当サイトの調査によりランキング掲載しています。
※ また、独立開業を考えている方に、当サイト「Founder」の利用がおすすめです。これまで多くの投資家・起業家のマッチングが生まれているので、投資家からサポートを受けられる可能性があるでしょう。
登録はカンタン1分で無料なので、こちらのフォームにメールアドレスを入力してみて下さい。


日本最大級の
起業家・経営者&投資家
マッチングサイト
創業10期目・年商10億円程度のベテラン経営者の方々にも
ご利用いただいております。
No.1
38,543名
No.1
7,163名
 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能 投資先が見つかる
投資先が見つかる 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK 売上アップ
売上アップ 集客数アップ
集客数アップ 取引先数100社増
取引先数100社増 ビジネスパートナーが見つかる
ビジネスパートナーが見つかる 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる
 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能
 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
 取引先数100社増
取引先数100社増
 売上アップ&集客数アップ
売上アップ&集客数アップ
 投資先やビジネスパートナーが見つかる
投資先やビジネスパートナーが見つかる
■個人事業主に必須な開業届とは?仕組みを徹底解説!
開業届は正式には「個人事業の開廃業届出書」といい、その名の通り個人事業主として開業することを税務署に申告するための届出書です。
個人事業主になると、事業の利益に対して所得税や個人事業税を課されるようになります。
そのため、開業届を出して税金を納める先の税務当局に個人事業主として開業することを報告する必要があります。
開業届を提出すると、個人事業主であるという税務署との公的な証明になります。
たとえば、屋号入りの印鑑作成、屋号での銀行口座の開設、銀行からの融資を受ける時などに、開業届を出していることが求められます。
個人の口座や印鑑を事業用として使用することもできますが屋号の口座や印鑑を持っておくと、取引先からの信頼アップにもつながりやすいと言えるでしょう。
また、個人の収支と個人事業主としての収支の区別をつけやすくなり、管理がしやすくなります。
開業届は個人事業主としての事業開始から1ヵ月以内に管轄の税務署へ提出するのが原則ですが、仮に1ヵ月を超えてしまっても、罰金や業務停止などのペナルティは発生しません。
とは言え、屋号を持ち個人事業主になったと明言するためにも、できるだけ早く提出しておくことが望ましいでしょう。
(出典:個人事業主のための開業届の書き方 | 山田税理士事務所)
■個人事業主が開業届を出す4つのメリットと3つのデメリット
開業届を提出することで個人事業主には嬉しいメリットがあります。
一方で、開業届を出すことでのデメリットもあるんです。
ここでは、開業届を出すメリットを4つとデメリットを3つ紹介していきます。
【開業届のメリットその1】青色申告による控除を受けられる
個人事業主として開業届を出す最大のメリットは、確定申告時に青色申告をして節税できること。
特典は多くありますが、その1つとして最大で65万円の特別控除を受けることができます。
その他、赤字を繰り越せるのもこれから個人事業主になりたい方には嬉しいポイントです。
青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書の提出をしなければいけません。
そして、この書類を出すには開業届を提出する必要があります。
なお、青色申告承認申請書は個人事業主になってから2ヶ月以内に出す必要があるので、開業届と一緒に提出しておくとよいでしょう。
青色申告のメリットについては下記の記事も参照ください。
参考記事
【初めての確定申告】青色申告書は本当にお得?白色申告との違いと申請方法について解説
【開業届のメリットその2】小規模企業共済制度を利用できる
個人事業主は会社員とは異なり、廃業した時に退職金制度がありません。
その代わりに、毎月積立金を払うことで、将来退職するときに所得を得られる仕組みが小規模企業共済制度です。
開業届は、この仕組みを利用するための必要書類となります。
掛金は自由に設定することができ、全額を所得から控除できる
退職、廃業時に退職所得として共済金を受け取れる
低金利で事業資金の貸付制度を利用できる
小規模企業共済制度を利用することで、上記のメリットが有るため節税効果が見込めます。
将来の備えを作りながら、節税もできる非常に便利な制度です。
【開業届のメリットその3】屋号で銀行口座を開設できる
屋号での銀行口座は、開業届を出さないと作ることができません。
屋号の銀行口座を持つと、確定申告のときに事業収支を把握しやすいだけでなく、取引先からの信頼度も上がります。
個人事業主は、法人と比べて信頼度が低いというデメリットがあるので、屋号の銀行口座を作成することは大きなメリットになるでしょう。
また、振込をする際にも、相手に認識されやすいというメリットがあります。
経費管理の観点だけで言えば個人で新規口座を開いてもよいので、屋号での口座開設にこだわる必要はありませんが、便利なので持っていて損はないでしょう。
【開業届のメリットその4】副業事業所得で申告できる可能性がある
開業届を出すことで、個人事業主になったという実感を得ることができますよね。
社会的にも、個人事業主と宣言できることで信用が高まるでしょう。
それと並行して、事業の所得を事業所得として申告できるようになります。
ただし、個人事業主として、本業を行っている場合は比較的認められやすいですが、副業で開業届けを出している場合は、認められづらい現状もあります。
副業の場合、本業の所得で生活費が賄われている場合、副業の収入が本業を超えていても、事業所得として認められないこともあるんです。
ただし、事業所得として認められれば、損益通算が行なえ、副業で赤字が出た場合、赤字のぶんを本業の所得から差し引き、所得税が減額されます。
これは大きなメリットであると言えますよね。
【開業届のデメリットその1】失業手当が受けられなくなる可能性がある
1つ目のデメリットは、失業手当に関してです。
会社員をやめて独立し、個人事業主として開業しようという方は注意です。
開業届を出すことで失業手当が受けられなくなる可能性があります。
そもそも失業保険は、退職後の生活の維持および再就職活動を容易にするための支援を目的としています。
開業届を提出すると、すでに事業があり再就職の支援が必要ないとみなされるので、手当の対象ではありません。
個人事業主になっても、収益が伸びず廃業になることもあるでしょう。
その際に、失業手当を受けられないのはデメリットであると言えます。
ただし、事業の収益により失業手当ての対象になる可能性もあります。判断は各地方自治体に委ねられているので確認が必要です。
【開業届のデメリットその2】扶養に入れなくなる可能性がある
2つ目のデメリットは、扶養に関してです。
現在、家族の扶養に入っている場合、開業届を出すことで扶養を外れる可能性があります。
社会保険の扶養に入る条件は、一般的に「年間収入130万円未満」と言われていますが、健康保険はその限りではありません。
「自営業者や個人事業主は収入にかかわらず、扶養に入れない」と定めている保険もあります。
家族の扶養に入っている場合は、開業届の提出により保険料が自己負担になる可能性があるので事前に規定をチェックしておきましょう。
個人事業主として開業しても、すぐに利益が出るとは限りませんよね。
その時に、保険料などの負担をしなくてはならないとなると、大きなデメリットになるでしょう。
【開業届のデメリットその3】事業所得で申告すると、副業が会社にバレる可能性がある
先程、メリットとして副業を事業所得として申告できる可能性があるとお伝えしましたが、
これにはデメリットも存在します。
それは、会社に副業がバレる可能性があるということ。
すべての自治体に当てはまるわけではありませんが、事業所得として申告すると、納税するべき金額が記載されている「特別徴収税額通知」が会社に送られてくるんですね。
その中に、どの所得で申告が行われたかが分かるようになっていると、副業がバレてしまうというわけ。
副業の収入を事業所得で申告すると、事業所得の欄の記載され、雑所得で申告すると雑所得の欄に記載されます。
つまり、「特別徴収税額通知」を見れば一発でどんな所得があるのかが分かってしまうので、副業での収入があることがバレてしまうことになるんですね。
ちなみに、雑所得で記載されている場合は、何によって収入を得たかまでは分かりません。
ネットオークションやフリマアプリなどの収入も、雑所得になるので副業をごまかすことはいくらでも可能です。
「特別徴収税額通知」を見て、副業がバレてしまうかどうかは自治体によって異なるため、事業所得で申告したいけど、会社に副業はバレたくない、という場合は予め自治体に確認しておきましょう。
【注意点】副業だと事業所得で申告するのは難しいのが現状
事業所得にすると、副業が会社にバレる可能性があるとお話しましたが、そもそも現状では、副業を事業所得として申告するのはとても難しくなっています。
なぜかというと、メリットで解説した「損益通算」が理由になっています。
副業を事業所得として申告できた場合、副業で赤字が出た時、その赤字を本業の所得から差し引くことで所得税を減額できるということでしたね。
この制度を悪用して、利益が見込めないのにも関わらず開業届けをだし、副業でわざと赤字をだすことで、所得税を減額し還付を受ける「脱税」行為に等しいともいえる行動をする人が増えてしまったため、副業を事業所得として申告するのが難しくなってしまいました。
ちなみに、副業を自分の判断だけで事業所得として申告してしまうと「修正申告」になる可能性もあるので、副業を事業所得として申告したい場合は必ず税務署に相談するようにしましょう。
■個人事業主が開業届を入手する4つの方法
開業届は、以下の4つの方法で入手できます。
- 税務署に取りに行く
- 国税庁のホームページからダウンロードする
- 国税電子申告・納税システムを使用する
- 専用のソフトを利用する
【開業届の入手方法その1】税務署に取りに行く
最寄りの税務署で受け取る方法です。ただし、提出先は事業を営む地域の管轄税務署のため、自宅と異なる場所で開業する際は注意が必要です。
【開業届の入手方法その2】国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁のホームページから、開業届をダウンロードすることも可能です。忙しい方や、税務署が遠方にある個人事業主の方はぜひ利用してみてください。
【開業届の入手方法その3】国税電子申告・納税システムを使用する
インターネットを利用して、開業届の入手から提出までを行う方法もあります。確定申告の手続きでおなじみのe-Taxでは開業届の作成や提出も取り扱っているため、活用してみるのも1つの手。
インターネット経由で全て終了できるのはとても楽ちんですよね。
ただし、e-Taxでは利用時間が限られているというデメリットもあるのでご注意ください。
【開業届の入手方法その4】専用のソフトを利用する
書類の入手や提出をまとめて行いたい場合には、上記でご紹介したe-Taxのほかにも専用のソフトを利用する方法があります。
たとえば「開業freee」を使うと、自宅にいながら開業届の提出が可能。
画面の指示に従って入力すれば誰でも簡単に提出できるため、試してみるのも良いでしょう。
個人事業主の開業手続き、開業届作成を無料でサポート | 開業 freee
■法人と個人事業主で手続きは違う?マイナンバーの扱いにも注意しよう!
開業届は、個人事業主だけでなく法人も提出することができます。
しかし、両者では手続きが異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
〇個人事業主が開業する場合の手続き
個人事業主として事業を開始するための必要書類は、上記で解説した「開業届」のみ。難しい手続きを想像していた方は驚かれるかもしれません。
そのほか、確定申告の際に青色申告書を使用したい個人事業主の方は「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。また、従業員を雇う場合には労働基準監督署での手続きが発生します。
青色申告についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページも合わせてチェックしておきましょう。
【初めての確定申告】青色申告書は本当にお得?白色申告との違いと申請方法について解説|Founder
青色申告でもっと節税!個人事業主でもできる青色申告の手順と6つのポイント!|Founder
個人事業主・個人経営で成功する10つのコツ!開業・集客・確定申告・節税対策パーフェクトガイド|Founder
〇法人が開業する場合の手続き
法人が事業を開始する際は、個人事業に比べると多くの書類や手続きが必要です。
主な手続きは以下の3つ。
- 定款を作成する
- 公証役場で認証を受ける
- 法務局で設立登記を行う
法人の場合は、個人が行う手続きと大きく異なり「設立登記申請書」「定款謄本」「印鑑届出書」「就任承諾書」など、さまざまな書類の提出が必要です。
手続きを経て会社を設立した後も、「法人設立届出書」をはじめ多くの書類を準備しなければなりません。
また、法人が事前に決めておくべき事項として「会社の形態」があります。
会社形態を決めるひとつの参考として、法人の場合は以下のページも合わせてチェックしておきましょう。
株式会社設立10のメリットとデメリット完全ガイド。個人事業主との違いは?|Founder
〇個人事業主はマイナンバーを記載する必要あり!
個人事業主の開業届には、マイナンバーの記載が必要です。書類の提出時にも、本人への成りすましなどの犯罪を防ぐため本人確認書類と併せてマイナンバーが記載された書類を提示します。
マイナンバーの確認書類は通知カードが一般的ですが、マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書でも問題ありません。
マイナンバーカードを発行している方は、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類の提出が免除されるためぜひ活用しましょう。
■個人事業主の開業届の書き方を徹底解説!
ここからは、実際の開業届の記入項目を参考にしながらそれぞれの書き方を解説します。まずは、開業届に記入する項目とその概要を押さえておきましょう。
このように、個人事業主の開業届にはさまざまな項目への記入が必要です。
「氏名」「生年月日」「マイナンバー」のようにすぐ記入ができる項目がある一方、「納税地」や「所得の種類」などの項目では書き方を迷う方がおられるかもしれません。
そこで、ここからは記入の際に注意が必要な項目をピックアップして、より詳しく解説します。上記の表と併せてチェックしてみてください。
〇記入に注意が必要な項目
【開業届の項目その1】所轄の税務署
個人事業主の開業届は、納税する地域を管轄する税務署へ提出します。したがって住民票を置いている地域が原則納税地となりますが、自宅以外で開業をする場合は開業先を納税地とすることも可能です。
各地域の税務署は国税庁のホームページからも検索できるため、事前に調べておきましょう。
【開業届の項目その2】提出日
個人事業主の開業届を提出した年月日を記載します。
副業であっても開業届の提出は開業日から1ヵ月以内が原則ですが、1ヵ月を過ぎた提出でも罰則はないため、自分のスケジュールに合わせて提出しましょう。
これは副業での開業届けでも同じです。
個人事業主としての開業日と提出日が同日となっても問題ありません。
【開業届の項目その3】納税地
【1】で個人事業主としての納税地に選んだ場所の住所を記載します。
「住所地」「居所地」「事業所等」の中から該当するものを選択しましょう。
【開業届の項目その8】職業
表記に決まりはありませんが「デザイナー」「士業」「飲食業」「コンサルティング」など、何の仕事をしているか分かるよう職業名を記載します。
個人事業主としてあなたがどんな事業を行っているかを示すところなので、できるだけ正確に記入しておくと良いでしょう。
【開業届の項目その9】屋号
店舗や事業所に屋号があれば記載しましょう。ない場合は空欄でも問題ありません。
屋号をつけておくと、個人事業主として取引先とやり取りなどをする時に認識されやすくなるでしょう。
その際、あまりにも奇抜な名前や、長すぎる名前だと不信感を抱かれてしまうので注意しましょう。
【開業届の項目その10】届出の区分
ここには、「開業」「事業所・事務所の新設・増設・移転・廃止」「廃業」などの区分が記載されています。
新規開業の場合には、「開業」を選択しましょう。
【開業届の項目その11】所得の種類
「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」の中から、該当するものを選択します。
【開業届の項目その12】開業・廃業等日
個人事業主としての開業日を記入します。
上述したように、開業届の提出日を開業日と見なしても問題ありません。思い入れのある日付や区切りの良い日など、自由に設定しましょう。
【開業届の項目その15】開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
この項目は上下2段に分かれています。
上段は「青色申告承認申請書」「青色申告の取りやめ届出書」の有無を選択します。
下段は、消費税に関する「課税事業者選択届出書」「事業廃止届出書」の有無を選択しましょう。
【開業届の項目その16】事業の概要
【8】では職業名を記載しましたが、ここでは事業の概要を記載します。
たとえば【8】で「飲食業」と記載した場合は、「パン屋の経営」「寿司屋の経営」など具体的に記しましょう。
個人事業主として、あなたが行っている事業を詳しく記載すればOK。
最近では、ライターやアフィリエイターなど、PCだけで完結する職業での開業も目立っているので、「伝わらないかもしれない」と思っても、記載しておくと良いでしょう。
【開業届の項目その17】給与等の支払の状況
個人事業主としての開業後、従業員を雇用する方もおられるでしょう。
ここには、雇用する従業員の人数や給与、賞与などを記載します。
「給与の定め方」の欄には、「時給」「日給」「月給」など支払方法を記載しましょう。
賞与を支払う予定があれば「月給+賞与」のように分かりやすく記載します。
【開業届の項目その18】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
個人事業主として従業員を雇うと毎月源泉徴収を納付しなければなりませんが、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておくと半期に一度の納付にまとめられるため便利です。
※ なお、独立開業をする為の資金が必要なら、SMBCモビットなどのカードローンへの申し込みがオススメです。
スマホやパソコンからネットだけで5分でカンタンに申し込みが完了します。あなたも100万円のお金を手に入れることができるので、今すぐ以下のリンクをクリックして申し込んでください。
【1番人気】SMBCモビットは来店不要で審査が完了。スマホアプリでカンタンに出金が可能です。
※アクセス数などを参考に当サイトの調査によりランキング掲載しています。
※ また、独立開業を考えている方に、当サイト「Founder」の利用がおすすめです。これまで多くの投資家・起業家のマッチングが生まれているので、投資家からサポートを受けられる可能性があるでしょう。
登録はカンタン1分で無料なので、こちらのフォームにメールアドレスを入力してみて下さい。


日本最大級の
起業家・経営者&投資家
マッチングサイト
創業10期目・年商10億円程度のベテラン経営者の方々にも
ご利用いただいております。
No.1
38,543名
No.1
7,163名
 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能 投資先が見つかる
投資先が見つかる 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK 売上アップ
売上アップ 集客数アップ
集客数アップ 取引先数100社増
取引先数100社増 ビジネスパートナーが見つかる
ビジネスパートナーが見つかる 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる
 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能
 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
 取引先数100社増
取引先数100社増
 売上アップ&集客数アップ
売上アップ&集客数アップ
 投資先やビジネスパートナーが見つかる
投資先やビジネスパートナーが見つかる
■開業届提出までのスケジュールをチェックしておこう!
開業届を入手しても、ただ記入して提出するだけではありません。書類を提出すれば個人事業主を名乗ることはできますが、具体的な開業の準備をしていなければ実際の開業は難しいでしょう。
そこで、開業届の提出日から逆算してスケジュールを掴んでおくことが大切。開業する業種によって違いはありますが、開業届の入手から提出までの大まかな流れは以下の通りです。
では、ひとつずつ見てみましょう。
【開業届提出の手順その1】開業届を手に入れ、必要な情報を整理
まずは開業届を用意します。冒頭でご紹介したように、開業届は税務署や国税庁のホームページなどから入手できるため、早めに用意しておきましょう。
また、開業するにあたって必要な情報を整理しておきます。たとえば、飲食店の経営の場合は店のコンセプトの企画や、事業計画書や創業計画書の作成、メニューの開発などが挙げられるでしょう。
開業に必要な資金を準備するのもこの時期です。開業までに多くの支出が考えられるため、自己資金だけで賄うのが難しい方は、融資を検討するのも良いでしょう。
融資を受ける場合には、無理のない返済計画を立てることが重要です。
【開業届提出の手順その2】店舗や事務所を契約する
自宅以外での開業を目指す方は、開業したい地域の立地を調査したり実際にさまざまな物件を比較してみたりと、賃貸契約の準備に取り掛かりましょう。
物件が決まったら、必要に応じて内装や外装の施工も行います。開業が目に見える形として近付いてくるため、だんだんと実感がわいてくる方も多いでしょう。
【開業届提出の手順その3】仕入れ先を選定する
業種によっては、材料の仕入れ先を決めておく必要もあります。予算や質など、仕入れにあたって自分が何を重視したいのかを明確にしておきましょう。
【開業届提出の手順その4】従業員を雇用する
従業員を雇用する場合は、開業の1ヵ月前には採用しておくと安心です。約1ヵ月かけて研修を行い、従業員の育成に力を入れましょう。
事業に役立つ資格があれば、取得しておくのもおすすめ。開業後は忙しくて時間が確保できない可能性もあるため、開業前の時間を有効に活用しましょう。
【開業届提出の手順その5】開業届を提出する
所得税法第229条に基づき、個人事業主としての開業届は原則開業後1ヵ月以内に提出します。開業している地域を管轄する税務署へ提出しましょう。
税務署の窓口へ持参するほか、郵送やインターネットサービスを利用することも可能です。
このように開業届の提出から逆算すると、遅くても開業の半年前から具体的な準備を始めるのが望ましいと言えるでしょう。
〇【注意!】開業届の提出が遅れると…?
上記で解説したように、副業であっても開業届は開業後1ヵ月以内に提出すると所得税法で定められていますが、1ヵ月を過ぎたからと言って罰金や罰則などはありません。開業後につい提出を忘れてしまっても、気が付いた時に提出すれば問題はないでしょう。
ただし、開業届を提出していなければ、個人事業主として店舗や事務所を構えて事業していることを第三者へ証明することはできません。したがって、融資や助成金に申し込みをしても審査に通らない可能性が高いと言えます。
また、確定申告の際に青色申告ができないため、次項で解説するメリットも得られないでしょう。罰則はないとは言え、個人事業主として開業をしたらできるだけ早く開業届を提出することをおすすめします。
■開業届と青色申告の違い&関連性を徹底解説!
開業届とは青色申告に必要なもの、という認識をもっている方はいませんか?確かに青色申告をするには開業届が必要になりますが、開業届を出したら青色申告ができるわけではありません。ここでは、この2つの違いと関連性を説明していきます。
開業届は個人事業主として事業を始めた報告です。そのため、開業届を出しても、確定申告の方法については定められていません。
青色申告は確定申告の様式の一つです。確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、事前に何もしていない場合は白色で申告することになります。白色申告ならば簡単な帳簿の提出のみで確定申告を終えられます。
一方で、青色申告の場合は簿記の形式が複雑にはなりますが、節税効果のある特典を多く受けることができます。ただし、青色申告は誰でもできるわけではありません。青色を希望する場合には事前に税務署長宛に青色申告承認申請書の提出が必要になります。
この申請書を提出するための条件が、開業届を出していること。そのため、開業届と同時に青色申告承認申請書を出す人が多く、この2つはよく同時に話題に上がります。
個人事業主として確定申告をするなら、65万円の控除を受けられる青色申告が圧倒的におすすめ。
開業届けと同時に、青色申告申請書の提出もしておきましょう!
■個人事業主は「青色申告承認申請書」も提出しておこう!
繰り返しになりますが確定申告には、「青色申告」「白色申告」の2つの方法があります。誰でも利用できる白色申告と異なり、青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
青色申告には以下のようにさまざまなメリットがあるため、開業届と併せてぜひ提出しておきたい書類でもあります。
【青色申告のメリットその1】最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
最も大きなメリットだと言える、青色申告特別控除。
複式簿記や帳簿付けなど一定の条件を満たすと、所得から最大65万円の控除が可能となります。
ただし、複式簿記は簿記の知識を要するため、個人事業主として開業したばかりの方にとっては難易度が高く感じられるかもしれません。
単式簿記で青色申告を行った場合の控除額は10万円です。
【青色申告のメリットその2】家族の給与を経費として計上できる
事業によっては、家族に協力してもらいながら経営する個人事業主の方もおられるでしょう。
配偶者や子ども、親戚など家族を従業員として雇用すると、家族への給与は「専従者給与」として経費にすることができます。
専従者給与と見なされるためには、年齢や従事期間などいくつかの条件に該当しており、なおかつ給与の金額が届出書に記載された範囲であることが前提です。
【青色申告のメリットその3】赤字の繰り越しが可能
個人事業主として事業を行っていると、赤字が出てしまう年もあるかもしれません。
青色申告では年度に出てしまった損失額を繰り越し、翌年の黒字との相殺が可能です。
赤字の繰り越し期間は最長3年間のため、その間に資金繰りを見直し、事業を立て直すこともできるでしょう。
赤字を繰り越すためには、赤字が出た年にもきちんと確定申告を行い、赤字であることを書面に残しておくのがポイントです。
【青色申告のメリットその4】30万円未満なら一括経費計上が可能
一般的には機材のように、高価なものを購入した場合には減価償却、つまり数年に分割して計上します。
その点、青色申告では30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」を利用して、一括して経費に計上することが可能。機材やパソコンなど高価なものや、材料費などをまとめて大量に購入する予定がある方は、節税効果が得られるでしょう。
青色申告承認申請書の提出期限は、開業してから2ヵ月以内とされています。提出を忘れてしまいそうな方は、開業届と同時に提出するのがおすすめです。
また、確定申告を行う前年の3月15日までに提出すれば青色申告が可能となるため、事業を開始してから提出したくなった場合にはできるだけ早く提出を済ませておきましょう。
※ なお、独立開業をする為の資金が必要なら、SMBCモビットなどのカードローンへの申し込みがオススメです。
スマホやパソコンからネットだけで5分でカンタンに申し込みが完了します。あなたも100万円のお金を手に入れることができるので、今すぐ以下のリンクをクリックして申し込んでください。
【1番人気】SMBCモビットは来店不要で審査が完了。スマホアプリでカンタンに出金が可能です。
※アクセス数などを参考に当サイトの調査によりランキング掲載しています。
■開業届をまだ出していない方は、お早めに!
今回は、個人事業主としての開業届の書き方や手続きの手順をご紹介しました。
開業届を出しておくと、税制面で優遇されるほかにも社会的信用を得られるなどのメリットがあります。
難しい手続きは必要ないため、これから個人事業主として開業予定の方は早めに準備を始めておくと良いでしょう。
既に開業している方も、提出はまだ間に合います。ぜひ検討してみてください。
また、起業資金・運転資金でお悩みの方は、当サイト「Founder」への登録も検討してみましょう。
Founderは投資家登録数No.1のサイトであり、数多くのエンジェル投資家が投資案件を探しています。これまでさまざまなマッチングが誕生しているため、あなたにもサポートを受けられるチャンスがあるでしょう。
登録はカンタン1分で無料なので、こちらのフォームにメールアドレスを入力してみて下さい。


日本最大級の
起業家・経営者&投資家
マッチングサイト
創業10期目・年商10億円程度のベテラン経営者の方々にも
ご利用いただいております。
No.1
38,543名
No.1
7,163名
 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能 投資先が見つかる
投資先が見つかる 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK 売上アップ
売上アップ 集客数アップ
集客数アップ 取引先数100社増
取引先数100社増 ビジネスパートナーが見つかる
ビジネスパートナーが見つかる
 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる
 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能
 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
 取引先数100社増
取引先数100社増
 売上アップ&集客数アップ
売上アップ&集客数アップ
 投資先やビジネスパートナーが見つかる
投資先やビジネスパートナーが見つかる
- 昨日の登録数
- 経営者8名 投資家1名
- 昨日の投稿数
-
経営者3件 投資家0件
- 先月のマッチング数
- 23組
- 先月の資金調達総額
- 7億円以上