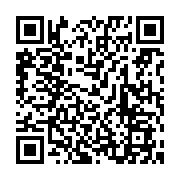NPO法人の設立手順と5つのメリット、デメリット。これでNPO法人が設立できる!
公開日:2018.5.21 | 最終更新日:2025.3.10
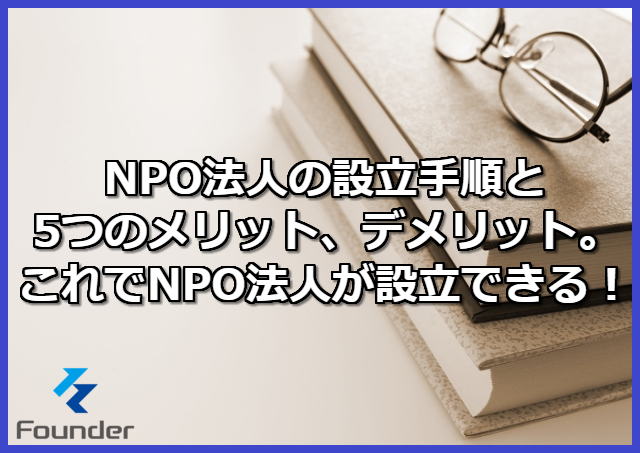
利潤目的ではなく、社会的課題の解決を目的に事業展開を行う組織はNPO団体と呼ばれます。
ある程度の規模に成長したNPO団体、あるいは今後活動範囲を拡大する予定のNPO団体には「法人化」という選択肢があります。NPO法人となれば組織としての信用力が高まり、より幅広い内容の活動展開が可能となります。
しかし、NPO法人設立がもたらすのはメリットだけではありません。いくつかのデメリットが存在することも事実です。
本記事では経営コンサルタント暦12年、NPO法人設立を専門的にサポートしてきた筆者が、NPO法人の設立手順と法人化のメリット、デメリットを紹介します。この記事を読めば、メリットとデメリットを比較考慮した上で、自団体の法人化についてしっかりと検討できるようになります。
■NPO法人とは?
NPOとは「Nonprofit Organization」の頭文字をとった略語であり、日本語に訳すると非営利組織という意味になります。
利益獲得を目的に活動する民間企業と異なり、NPOは公共の利益実現を目的とした活動を行う点が特徴です。政府や自治体、企業では対処しづらい市民のニーズに対して、民間の立場から応えるという社会的役割が期待されています。

活動内容は団体によってさまざまですが、里山の保全と育成を目的としたNPO、町並みの保存活動に取り組むNPO、地雷除去を行うNPOなどが存在します。
NPO団体には組織形態や団体メンバーの特色によって異なる呼び方が用いられます。市民が中心となって組織されている場合は「市民活動団体」と、メンバーの多くがボランティアで構成されている場合には「ボランティア団体」と呼ぶのが一般的です。
そして、法人格を与えられたNPO団体に与えられる呼称が「NPO法人」です。
NPO法人には団体の活動に必要となる資金や運営のための資金を集めるために、自団体の主要活動内容以外の事業を実施することが認められるようになります。法的な位置づけが明確化されるため、社会的なプレゼンスが高まり、NPO団体への信頼性も増すなどのメリットがあります。
■NPO法人設立の手順
NPOが法人格を取得するためには、特定非営利活動法で定められた要件をNPO団体が満たしている必要があります。
【条件1】NPO団体が行う活動範囲の制限
NPO団体の活動は、特定非営利活動法(NPO法)によって20分野にのみ認められています。NPO法人として認められるためには、団体が以下の20分野のいずれかに属する活動を行っていなければなりません。
(内閣府NPOホームページより:https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/nposeido-gaiyou)
【条件2】NPO活動に対する規制
法人化が認められるためには、NPO団体が特定非営利活動法で定められた以下の条件を満たしている必要があります。
| NPO活動に関する規制 |
【条件3】法人申請のための必要書類の作成と提出
NPO法人の設立には、以下に記載した申請書を作成した上で担当の所轄庁に届出をしなければなりません。
| NPO法人設立に必要な書類 |
|
(内閣府NPOホームページより:https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninshouseido)
届出先の所轄庁は、NPO団体の事務所が所在する都道府県です。審査では活動内容などの事前調査は実施されず、あくまで書類審査のみで認証が行われますが、それでも2ヶ月程度かかると見込んでおいた方が良いでしょう。
無事に法人設立の認可が下りると、所轄庁から認証通知が送付されます。
通知を受け取ってから2週間以内に法務局で設立の登記を行います。法務局で登記手続きを終えた後、改めて設立登記完了届出書を登記事項証明書や財産目録などと一緒に所轄庁に提出し、設立手続きは完了です。
次からはNPO法人設立のメリットについて、ご紹介します。
■【NPO法人設立のメリット1】低コストで設立可能
民間企業を設立する際には、最低資本金など会社が準備する資金に関する法的規制がかかわってきます。
しかしNPO法人の場合、資本金や出資金に関する法律は存在しません。このため資本金が0円でも法人設立が可能です。

(出典:NPO法人設立なら【KiND行政書士事務所】49,800円!返金保証付!最短5日で申請可能!)
また民間企業の設立時には、定款認証代や収入印紙代、登記時の登録免許税などを支払わなければなりません。しかしNPO法人の場合、こうした設立経費はすべて免除されます。さらに法務局に設立登記を行う際に支払う数万円の登録免許税も支払う必要がありません。
必要になるのは法人用の印鑑作成費、法人役員の住民票を請求するための費用、登記手続きに要する交通費や通信費くらいでしょう。
法人の設立手続きを行政書士など法律の専門家に代行してもらう場合はその分の追加費用が発生しますが、それでも民間企業を設立する場合よりも、費用を低く抑えられます。
ただし設立時の費用とは別に、法人の運営資金はしっかり準備しておかなければなりません。
資本金0円でも設立可能というのは、一見すると大きなメリットのように思えます。けれども資本金0円というのは、NPO法人に準備資金が一切存在しない状態だということでもあります。赤字続きでも最低でも2~3年程度は企業運営に支障が出ずに済む程度の資金を準備しておくのが望ましいでしょう。
■【NPO法人設立のメリット2】大きな社会的信用を得られる
NPOであれば団体規模にかかわらず、事務所用オフィスの賃貸を契約するほか、水道・電力会社との契約、プロバイダとの通信契約、企業や法人との各種契約などを結ぶ必要があるでしょう。
しかし、契約を結ぶ際には一定の社会的信用力が認められなければなりません。契約の種類によりますが、NPO団体が法人格を備えていない場合には契約締結に応じてもらえない可能性もありえます。
法人格がないNPO団体が何らかの契約・取引を結ぶ際には、代表者個人の名義で行わなければなりません。
しかし、こうした手法をとった場合、NPO代表者が交代、あるいは死亡した際の手続きが煩雑化するデメリットがあります。このため、ある程度NPO活動が安定したら法人化を検討することをおすすめします。
また法人化することで、一般社団法人や一般財団法人などの非営利団体に比べて、はるかに高い地名度や社会的信頼を得られます。金融機関からの信用も得やすく、NPO活動を展開する上での資金調達がよりスムーズになる効果も期待できます。
また、法人格を取得するとNPO団体の名義で不動産を保有できるほか、法人名での銀行口座開設なども可能となります。さらに前述の通りNPO法人向けの助成金などもあり、資金調達面でも有利になるためNPOの活動を拡大しやすくなります。
さらに、法人化には団体の認知度を向上させる効果も期待できます。知名度が上がればNPOの活動内容に賛意を示す協力者や、優秀な人材が集まりやすくなると考えられるためです。
■【NPO法人設立のメリット3】税制優遇を受けられる
民間企業と異なり、収益事業を行わないNPO法人には税制上いくつかの優遇措置が設けられています。
現在、NPO法人に認められている税制優遇は大きく分けて3種類存在します。
法人税
NPO法人は税法上「公益法人等」として扱われます。これらの団体が特定非営利活動によって得た所得は法人税の課税対象とはなりません。ただし収益事業によって得た所得は課税対象となりますので注意が必要です。
なお団体規模に応じて割り当てられる法人住民税の均等割分は原則として納めなければなりません。しかし、地方自治体によってはNPO法人向けの減税制度を設けている場合があります。納税前に、あらかじめ所轄庁のWebサイトなどで確認しておくと良いでしょう。
消費税
介護保険法などで定められた非課税取引の対象となる介護・福祉用商品やサービスの購入を除き、NPO法人であっても消費税は支払わなければなりません。ただし、NPO法人の設立時からカウントして2期目までは消費税の納税義務は免除され、3期目以降も課税売上高が年間1,000万円以下であれば免除されます。
したがって、小規模なNPO法人であれば消費税については免税となる可能性が高いといえるでしょう。ただし免税が認められる場合でも、商品・サービスの仕入代金や購入費用にかかる消費税は納税しなければなりません。
印紙税
印紙税法上、NPO法人は営業者としては扱われません。このためNPO法人の収益事業に関する領収書であっても印紙税の免税対象となります。
しかし、これはあくまで領収書に貼る印紙に関する話です。契約書などに貼る印紙は非課税対象とはなりません。どのような種類の印紙が課税対象とみなされるか気になる人は、事前に国税庁のホームページで確認しておくと良いでしょう。
■【NPO法人設立のメリット4】補助金・助成金制度を利用できる
NPO団体は非営利目的の活動を行うため、運営の資金繰りに苦労している団体も少なくありません。こうした経済的な悩みを抱えるNPO法人を支援するため、地方自治体などの行政機関の中には補助金・助成金制度を整備していることがあります。

(出典:NPO法人設立なら【KiND行政書士事務所】49,800円!返金保証付!最短5日で申請可能!)
NPO法人への助成金は、活動分野に応じて支給されます。このため特定分野のNPO法人を対象とした助成金は、その分野にかかわる活動を行うNPO法人にしか受け取れません。たとえば介護・福祉活動を推進するNPO法人向けの助成金は、介護関係のNPO法人だけが受給資格を有します。
また、助成金を申請したNPO法人すべてに助成金が支給されるわけではありません。審査を通過し、受給基準を満たしていると認められた団体だけが支給対象となります。
これらの助成金や補助金は金融機関から受ける融資と異なり、返済義務は存在しません。このためNPO法人の運営を円滑化する上で重要な収入源のひとつとして重宝するでしょう。
ただし、最近は助成団体の基金総額は頭打ちになる傾向があります。特に人気の高い助成金は競争率が10倍以上に達することも珍しくありません。助成金が支給されるより、支給されない確率の方が高いというのが実情です。
したがって、助成金や補助金を頼りにした法人運営の計画は極めて危険です。
助成金や補助金はあくまでNPO法人の運営をサポートするための資金とみなし、事業の収益のみで健全に運営ができるように事業計画を立案することが重要です。
■【NPO法人設立のメリット5】優秀な人材確保が可能に
法人化により社会的信用力を高めることで、優秀な人材も集まりやすくなります。
民間企業と同様、NPO団体も職員を雇用しなければなりません。
設立当初は少数の人員で足りていても、活動範囲を広げるうちに労働力が不足することも考えられます。このため継続的な人材確保は必須事項です。そして集める人材はできるだけ優秀な人材であることが望ましいでしょう。
優秀な人材を集める上で、NPO法人という社会的ステータスが役に立ちます。
そもそもNPO法人は一般社団法人などの法人と比較すると、設立認可のための審査基準のハードルが高くなっています。つまり法人化は、そのNPO団体が厳しい審査を通過できたという証明になるため、高い信頼が寄せられるのです。
また社会的信用という観点以外にも、組織としての安定性をアピールする上でも法人化は役立ちます。
法人化しておけば、代表者が止むを得ず退任せざるを得なくなった場合でも、団体内で他の人材を選任すれば組織としての活動は継続可能です。しかし法人化していないと、代表者の代理を立てるには非常に煩雑な手続きが必要となるため、活動継続が危ぶまれます。
NPO法人への入会を検討する人の中には「この団体で長期的に活動できるかどうか」という懸念を抱える人もいます。法人化はこうした懸念を払拭する上で大いに役立つことでしょう。
■【NPO法人設立のデメリット1】活動内容・範囲に制約が生じる
ここまでNPO法人を設立するメリットを解説してきましたが、一方で法人化にはいくつかのデメリットも存在します。
NPO法人は法人設立の届出をする際に所轄庁に定款や設立趣旨書を提出します。これらの書類にはNPO法人の「主たる活動内容」を記載しなければなりませんが、前述の通り、この内容はNPO法で定められている20分野の非営利活動のいずれかに該当しなければなりません。
たとえば「保健、医療または福祉の増進を図る活動」なら介護サービスを行う団体や介護タクシーサービスを運営する団体、配食サービスを実施する団体が該当するでしょう。また「学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動」であれば、ダンスサークルやスポーツジムを運営する団体、スポーツ指導者を教育する団体、伝統文化の継承・保存のために活動する団体などが当てはまります。
NPO法人は、NPO法で定められた分野以外の非営利活動は行えません。万が一活動分野を変更する場合には、定款を変更した上で所轄庁に再度届出をし、改めて認証手続きを行う必要があります。
しかし、定款の内容を修正するためには、理事会で役員からの合意を取り付け、総会を開催して決議をとる必要があります。法人化前と違い、重大な組織の意思決定を行う際には理事会や総会に賛否を問わなければならないため、どうしても時間がかかってしまいます。このため、NPO団体の活動方針や事業内容を変更することが難しくなるのです。
したがってNPO法人を設立するにあたっては、自団体の活動が20分野のいずれに該当するかを確認し、将来的に変更する可能性などについてもしっかりと検討しておかなければなりません。
■【NPO法人設立のデメリット2】設立に時間がかかる
NPO法人を設立するためには、非常に煩雑な手続きが必要となります。この手続きは数週間程度では終わりません。かなり長い時間がかかるため、やり直しがないよう慎重に取り組むようにしましょう。
最初に行う作業は所轄庁に提出する書類作成です。この作業だけで2週間から1ヶ月程度はかかると見込んでおいた方が良いでしょう。
設立趣旨書や定款、事業計画書、収支予算書、役員名簿などを作成しなければならず、役員の住民票を請求して取り寄せるといった作業も必要となります。行政書士などの専門家に依頼せずに自力で作成する場合、すべての書類を準備し終えるまでに2ヶ月以上かかる可能性もあります。
無事にすべての設立書類を作成し終えたら、次は書類を所轄庁に提出します。しかし所轄庁に書類を提出しても、すぐに審査が開始されるわけではありません。一般市民に対し設立申請書類の一部を公開する「縦覧」が、提出後2ヶ月間にわたり行われるためです。
縦覧期間中は所轄庁での書類審査は行われません。縦覧が終わってから、ようやく所轄庁は設立の認証審査を始めます。
所轄庁が認証審査を始める時期は「縦覧期間終了後2ヶ月以内」と法律で定められています。
しかし縦覧終了後すぐに審査が始まるのか、あるいは2ヶ月間の期限一杯まで審査が引き延ばされるのかは所轄庁の判断によって異なります。このため、基本的には最大2ヶ月はかかると考えておくべきでしょう。
所轄庁での審査を通過した後は、法務局に登記申請を行う必要があります。
ただ、登記申請は所轄庁での審査ほど多くの時間はかかりません。通常は登記申請書類を提出して、3日から1週間程度で申請が受理されることになります。
ここまでをまとめると、設立書類の作成から法務局での登記申請までに半年程度の期間は見込んでおくべきだということがわかります。

(出典:NPO法人の設立 | 司法書士・行政書士のトリニティグループ - Trinity-group)
ただし、上記はあくまで標準的な目安でしかありません。設立申請数の多い東京都や大阪府などの地域では、役所での審査期間だけで4ヶ月かかることも珍しくありません。
このように法人設立には大変多くの時間がかかります。法人化を決めた場合は、速やかに申請のための準備を始めるようにしましょう。
■【NPO法人設立のデメリット3】事務処理の厳正さ、情報公開の義務
法人化前と比べ、NPO法人には厳正な事務処理作業が義務付けられるようになります。
たとえば簿記を作成する場合、法人化前と違い簿記の表記方法はいい加減なものでは認められず、正式な表記方法で記載する必要があります。このため簿記に詳しい経理担当者を新しく雇用するか、あるいは税理士など会計事務所に簿記作成を委託しなければならなくなります。
またNPO法人には、事業報告書や収支計算書などの会計資料の作成と、それら資料を市民に向けて情報公開することが法的に義務付けられています。
情報公開が義務付けられている資料は、以下です。
| 情報公開義務のある資料 | ・事業報告書 ・収支計算書 ・貸借対照表 ・財産目録 ・役員名簿 ・社員、正会員名簿 |
さらにNPO法人の事務所にも上記書類や定款などを備え付け、資料公開を請求した市民に閲覧させる義務も存在します。
これらの書類を年度ごとに毎回作成し、所轄庁に提出しなければなりません。
また簿記作成以外にも、オフィス移転の際に煩雑な手続きが必要となるのもデメリットといえるでしょう。
事業所を開設する際には、特定のオフィスを事務所として定めることを所轄庁に届出する必要があります。オフィスを移転する場合には、所轄庁に事務所の住所変更する旨を改めて通知しなければなりません。さらに移転先の住所が現在の所轄庁と異なる場合には、移転先の所轄庁にも届出を行う必要があります。
また定款の変更手続きも役員会議や総会で問い、承認を受けなければならないため、時間がかかります。
NPO法人という組織形態は、組織の事業展開や方針転換を迅速に実施するのに適しているとはいえません。
上記で取り上げたように、法人化で増加した事務作業を消化するには、専門家に委託するか、社員を増やすかのどちらかを選択することになるでしょう。しかしいずれにせよ、ある程度のコスト増加は覚悟しておかなければなりません。
■【NPO法人設立のデメリット4】税務申告が必要
法人化により、NPO団体は納税主体として税務署に認知されるため、税務申告義務が発生します。
先述の通りNPO法人は公益法人とみなされるため、特定非営利活動を通じて得た所得は課税対象となりません。また本来であれば全法人が負担しなければならない法人住民税も、収益事業をしないNPO団体については必要な手続きを行えば減免される可能性があります。
このように数々の税制優遇措置が存在する一方で、デメリットもあります。
NPO法人が税務申告をすると、税務署がNPO法人の経営実態を詳しくチェックするようになるのです。その結果、税法上の収益事業に該当する非営利事業で得た収益については法人税の課税対象とみなされるようになります。このほか、法人税のほか法人事業税、法人県民税、市町村民税についても同様です。
もちろん、そもそも収益事業を行っていないNPO団体は税務申告を行う義務自体がありません。しかし義務の有無にかかわらず、法人を設立すると所轄庁から確定申告書が自動的に送付されてきます。
自団体が税務申告の義務があるかどうかわからない場合は、申告書を作成する前に一度所轄庁に問い合わせしておくと良いでしょう。
■【NPO法人設立のデメリット5】10人以上の社員が必要
NPO法人は設立時に、10名以上の社員が在籍している必要があります。
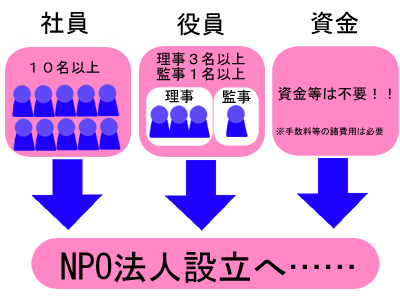
NPO法人における社員とは「法人の目的に賛同して入会した個人・団体」と法的に定められています。民間企業における従業員とは違い、総会に出席してNPO法人の運営に参加する個人・団体のことを指します。
未成年や外国人居住者の人も社員になることが可能です。また役員と違い社員には親族制限はありません。このため、役員の配偶者や親族も社員として認められます。さらに役員も社員とみなされるため、実質的に集めなければならない社員数は10名よりずっと少なくて済みます。
このように考えると、10人という社員数の規定は意外と簡単に達成できるのではないかと思う人もいるでしょう。
しかし頭数を揃えることだけを優先し、個々人の適正や能力を無視して社員として迎え入れていると後々後悔することになりかねません。なぜならば、NPO法人の社員に、総会で1人1票の議決権が与えられるからです。
株式会社の場合、株主総会では持株数に応じて議決権が分配されます。しかしNPO法人においては全社員に平等に議決権が与えられています。このため数合わせのためだけに、好ましくない人を社員として迎え入れた結果、活動内容の変更など重要な議題に関して意見が通りにくくなる可能性もあります。
したがって社員の選定は、慎重に進めることが望ましいといえます。
■NPOを法人化して経営を有利に
NPOの法人化は、団体の社会的信用力を向上させるほか税制優遇を受けられるようになるなど、団体の活動範囲拡大に役立つメリットがいくつも存在します。
しかしNPO団体設立の手続きには莫大な時間がかかる上、無事に設立できても経理作業や税務申告などの手続きに多くの時間を割かなければならなくなります。また、そもそも法人化の条件も簡単にクリアできるものではありません。
上記のデメリットへの対策としては、社員の新規増員、外注などの方法が考えられます。しかし、いずれにせよある程度の運営コスト増加は覚悟し、新たに資金調達を実施する必要があるでしょう。


日本最大級の
起業家・経営者&投資家
マッチングサイト
創業10期目・年商10億円程度のベテラン経営者の方々にも
ご利用いただいております。
No.1
38,599名
No.1
7,172名
 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能 投資先が見つかる
投資先が見つかる 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK 売上アップ
売上アップ 集客数アップ
集客数アップ 取引先数100社増
取引先数100社増 ビジネスパートナーが見つかる
ビジネスパートナーが見つかる
 無料で投資家が見つかる
無料で投資家が見つかる
 1,000万円の事業資金調達が可能
1,000万円の事業資金調達が可能
 資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
資金繰りやつなぎ資金のサポートもOK
 取引先数100社増
取引先数100社増
 売上アップ&集客数アップ
売上アップ&集客数アップ
 投資先やビジネスパートナーが見つかる
投資先やビジネスパートナーが見つかる
- 昨日の登録数
- 経営者4名 投資家0名
- 昨日の投稿数
-
経営者6件 投資家0件
- 先月のマッチング数
- 23組
- 先月の資金調達総額
- 7億円以上